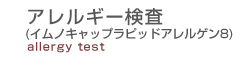起立性調節障害
起立性調節障害とは?
起立性調節障害(OD)は、自律神経系の機能不全によって様々な症状が現れる疾患です。思春期に多くみられますが、大人にも発症することがあります。
自律神経は、循環器、消化器、呼吸器など、体の様々な機能を無意識のうちに調節する神経系です。起立性調節障害では、この自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが崩れることで、立ち上がった際に血圧が適切に上昇せず、脳への血流が不足しやすくなります。その結果、めまい、立ちくらみ、動悸、息切れ、倦怠感、頭痛、腹痛、吐き気などの症状が現れます。
起立性調節障害の原因
大人の起立性調節障害の原因は様々で、明確な原因が特定できない場合も多いですが、一般的には以下のような要因が関わっていると考えられています。
- 生活習慣の乱れ:睡眠不足、不規則な食事、運動不足など
- ストレス:過剰な精神的負担、職場や家庭環境での問題など
- 身体的要因:脱水、貧血、低血圧、感染症、甲状腺機能低下症など
- 薬の副作用:降圧剤、利尿剤など
- 体質:自律神経の反応性が低いなど
- 他の疾患に伴う
また、パーキンソン病、糖尿病、多系統萎縮症などの神経疾患や、心不全や不整脈などの循環器疾患など、他の疾患に伴って起立性調節障害の症状が現れる場合もあります。
こんな症状があるときはご相談ください
- 朝起きられない、午前中調子が悪い
- 立ちくらみ、めまい
- 動悸、息切れ
- 頭痛、腹痛
- 倦怠感
- 食欲不振、吐き気
- 気分の落ち込み、不安感
- イライラしやすくなる
- 集中力の低下
- 多汗、手足の冷え など
少しでも気になる症状がある場合は、お気軽にご相談ください。
症状が日常生活に支障をきたすほど強い場合や、長期間続く場合は、早めにご受診ください。
起立性調節障害の検査について
起立性調節障害の診断は、問診や血圧・脈拍の他、以下のような検査を組み合わせて診断を行います。どの検査が必要かは、個々の症状や状態によって異なりますので、まずは一度ご相談ください。
- 起立負荷試験
起立性調節障害の診断に最も重要な検査が起立負荷試験です。この検査では、ベッドに横になった状態から立ち上がった時、または立ったまま安静にしている時の血圧と脈拍の変化を測定します。 - 血液検査
貧血や甲状腺機能異常など、起立性調節障害に似た症状を引き起こす他の疾患を除外するために、血液検査が行います。血液検査では、赤血球数、ヘモグロビン濃度、甲状腺ホルモン値などを測定します。 - 心電図検査
不整脈など、心臓に関連する疾患を除外するために行います。
起立性調節障害の治療について
起立性調節障害の治療は、一般的には生活指導を中心とした非薬物療法と、必要に応じて薬物療法を組み合わせた治療を行います。
生活指導
起立性調節障害の治療の基本は生活習慣の見直しです。規則正しい生活習慣を身につけ、症状の悪化を防ぐことが重要です。
- 睡眠
睡眠不足は症状を悪化させるため、十分な睡眠時間を確保することが大切です。毎日同じ時間に寝起きし、睡眠リズムを整えるようにしましょう。睡眠の質を高めるために、寝る前のカフェインやアルコールの摂取は控え、リラックスできる環境を作ることも重要です。 - 食事
塩分と水分の摂取は、血圧の維持に深く関わっているため、意識的に摂るようにしましょう。ただし、過剰な塩分摂取は高血圧のリスクを高めるため、バランスが重要です。 - 運動
適度な運動は、血流を改善し、自律神経の機能を整える効果が期待できます。ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない範囲で体を動かす習慣を身につけましょう。 - 入浴
入浴は、リラックス効果があり、自律神経のバランスを整える効果も期待できます。ぬるめの湯にゆっくりと浸かり、リラックスするようにしましょう。熱いお風呂は、逆にめまいなどを引き起こす可能性があるので注意が必要です。 - その他
長時間立っていることを避け、こまめに休憩を取ることも重要です。また、急な立ち上がりは症状を悪化させる可能性があるので、ゆっくりと立ち上がるようにしましょう。朝、起き上がるのが辛い場合は、布団の中で軽く手足を動かしてから起き上がるようにすると、症状を軽減できる場合があります。腹筋や背筋を鍛えることも効果的です。
薬物療法
生活指導だけで症状が改善しない場合は、薬物療法の併用も検討します。